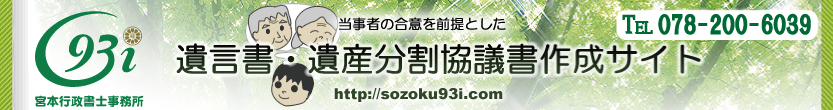神戸市にて遺言公正証書を代行いたします。
公正証書遺言
作成方法
①証人2人以上の立ち会いがあること
・・・*1
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・・・*2
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は、閲覧させること
・・・*3
④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印すること
・・・*4
⑤公証人の署名・押印
公正証書遺言作成時の注意点
*1について(証人について)
証人はだれでもなれるというわけではありません。
例えば、
①単独では契約ができない未成年者や
②遺言を行おうとしている者の推定相続人(贈与を受けようとしている者であれば受遺者)及びこれらの配偶者・直系血族
③あまりありませんが、公証人の配偶者、公証人の4親等以内の親族、公証人の書記・使用人などは証人となることはできません。
(民法974条)
*2について(遺言書の原案作成方法)
遺言者が話すことができない場合は、「口授」ではなく、例えば「通訳人の翻訳」や「遺言者本人が記載した文書」により遺言書の趣旨を公証人に伝えても良いとされています。
(民法969条の2第1号)
なお、実際にご依頼を頂いた場合には、行政書士宮本健吾がお客様のご要望をお聞きし、
ますは、遺言公正証書の原案を作成します。
その後、遺言者の方にて、内容を確認してもらいまして、追加したい遺言内容があれば、追加をし、なければ、行政書士宮本健吾と公証人とが打ち合わせをし、公正証書を作成していくことになり、お客様は公正証書遺言の最終案に同意後、公証役場にて、署名・押印をすることになります。
このような場合、上記の「口授」に反しているとも見えますが、古い判例として、昭和9年7月10日の判例によれば、このような遺言公正証書の作成方法も問題がないとされています。
*3について(公正)証書原案の確認作業
遺言者本人の耳が聞こえない場合や目が見えない場合も考えられます。
このような場合は、閲覧をさせたり、通訳人に通訳をさせることも可能です。
(民法969条の2第2号)
*4について(署名・押印)
あまりないことではありますが、脳卒中などで上半身不随となってしまったような場合、遺言者が署名押印できない場合があります。
そのような場合には、公証人が署名できない理由などを記載して、当該署名に代えることができます(民法969条第4項)
公正証書遺言作成時に必要な書類
・遺言者の実印と印鑑登録証明書
上記持ち物中、印鑑登録証明書は発行後3カ月以内の物を使用します。
なお、同一公証役場の同一公証人に対して、遺言書の書き直しなどを依頼した場合は、既にお互いに見知っているため、印鑑登録証明書は必要なくなる場合があります。
・戸籍謄本・住民票
遺言をするにあったて遺留分の割合の確認及び相続人の確認をするために、提出を求められる場合があります。(法律上は必ずしも提出しなければならないとはされていませんが、将来の紛争を避けるためには提出しておいた方がよいでしょう。)
戸籍謄本に関しては、遺言者と受遺者との続柄が分かるようにしておきましょう。
また、遺言によって財産をもらう予定の者を受遺者というのですが、当該受遺者の住民票が必要となる場合もあります。
・証人の身分確認証
証人の身分確認のために必要となります。
通常は顔写真付きの公文書(運転免許証など)を公証人に見せます。
・通帳の写しなど
財産を確認すると共に、公正証書作成手数料を計算するためにも使用します。
その他、生命保険に加入されている方の場合は、生命保険証書。
株式を御持ちの方は株券などのコピーが必要となります。
財産の有無及び財産の種類によって必要書類は大きく異なりますので、
お客様毎に必要書類をアドバイスさせてもらいます。
公正証書遺言のメリット
公証人の元に原本が保管される(公証役場というところに元本が保管されることになります。)ため内容の変造・紛失の危険がない。
家庭裁判所にて検認の手続きが必要なくなること。
公証人が関与する事により、遺言の効力が問題になる危険性が少ないこと
などが挙げられます。
公証人手数料
公証人に対する手数料が必要となってきます。
具体的には、
| 目的財産の価格 | 手数料の額 |
|---|---|
| 100万円迄 | 5,000円 |
| 200万円迄 | 7,000円 |
| 500万円迄 | 11,000円 |
| 1,000万円迄 | 17,000円 |
| 3,000万円迄 | 23,000円 |
| 5,000万円迄 | 29,000円 |
| 1億円迄 | 43,000円 |
| 1億円を超える部分については、 1億円を超え、3億円まで |
5,000万円毎に13,000円 |
| 3億円を超え10億円まで | 5,000万円毎に11,000円 |
| 10億円を超える部分 | 5,000万円毎に8,000円 |
※1全体の財産が1億円以下の時は、上記の表に加えて、手数料として、11,000円が加算されます。
※2 公証人が出張をして、公正証書を作成する場合は、上記金額に1.5を乗じた金額と日当10,000円がかかります。
※3 上記公証人手数料の計算は、財産の相続又は遺贈を受ける人毎に必要となります。
具体的には、財産の相続又は遺贈を受ける人が2人おり、
1人は、600万円をもらう予定であり、もう一方が1,300万円をもらう予定の場合、
600万円をもらう予定の人の手数料が、17,000円。
1,300万円をもらう予定の人の手数料が、23,000円。
これらを合わせて考えて行く必要があります。
| 遺言相続専門サイト |
| 任意後見公正証書 |
| 料金一覧 |
| 相続お問い合わせ |
| 遺言お問い合わせ |
| 事務所紹介 |
| 所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5丁目1-27 第百生命神戸三宮ビル7階 >>詳細地図 |
| 電話番号 | 078-200-6039 |
| FAX番号 | 050-3660-8633 |
| mail@sanda93i.com | |
| URL | http://sozoku93i.com/ |
| 事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
| 事務所長 | 宮本 健吾 |
| 業務範囲 | 兵庫県は神戸市及び 日本全国に対応。 |
| 相続欠格 |
| 相続人の廃除 |
| 相続財産の範囲 |
| 遺留分 |
| 自筆証書遺言 |
| 遺言公正証書 |
| 秘密証書遺言 |
| 遺言書と共に |
| 遺言執行者の役割 |
| 公正証書遺言のススメ |

|
LED照明(OEM)→